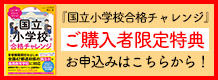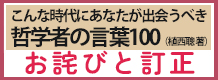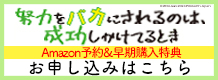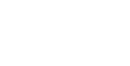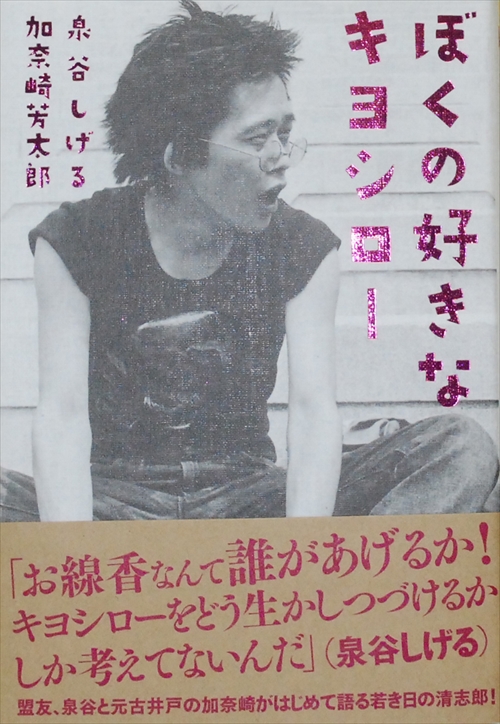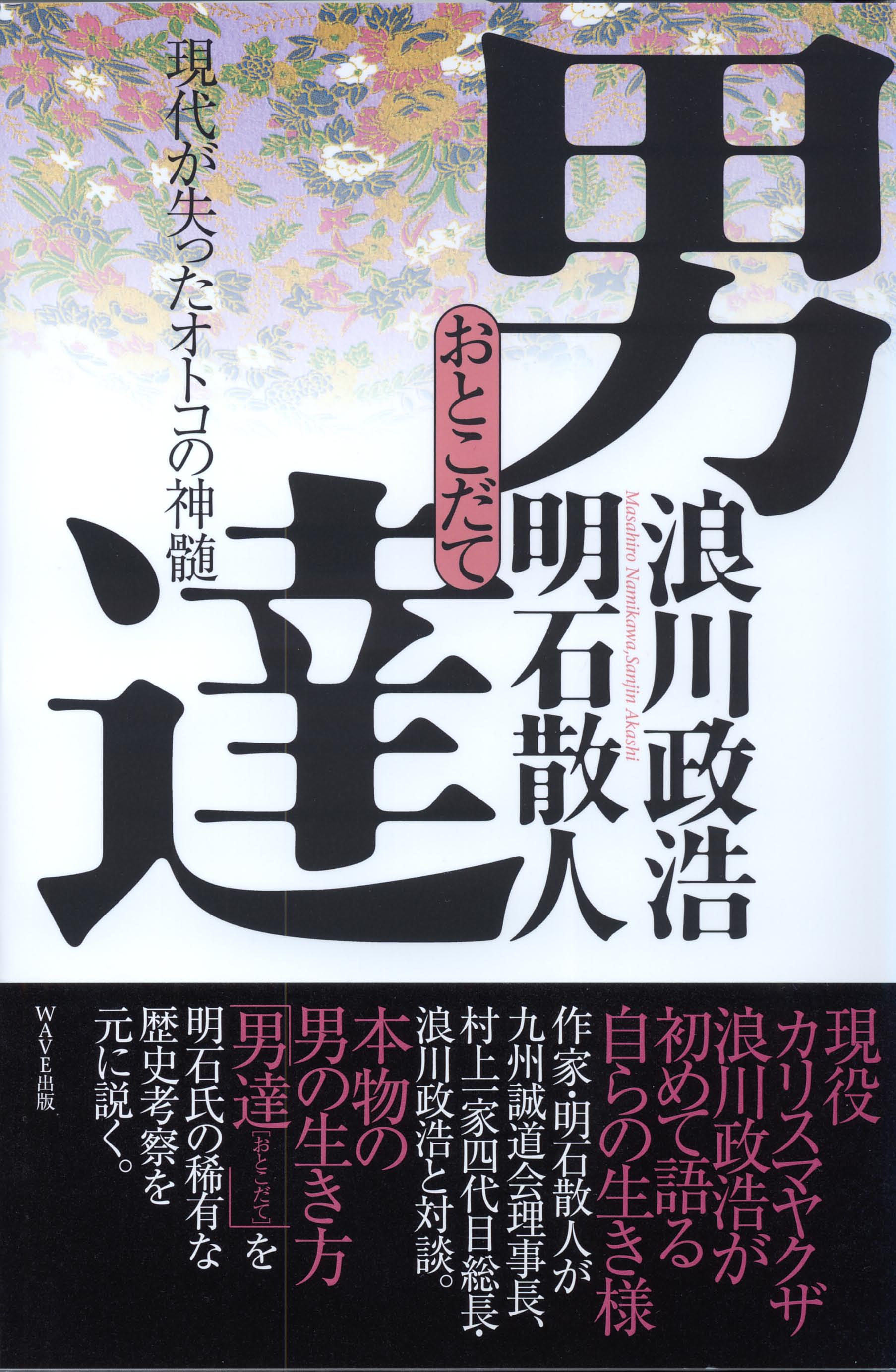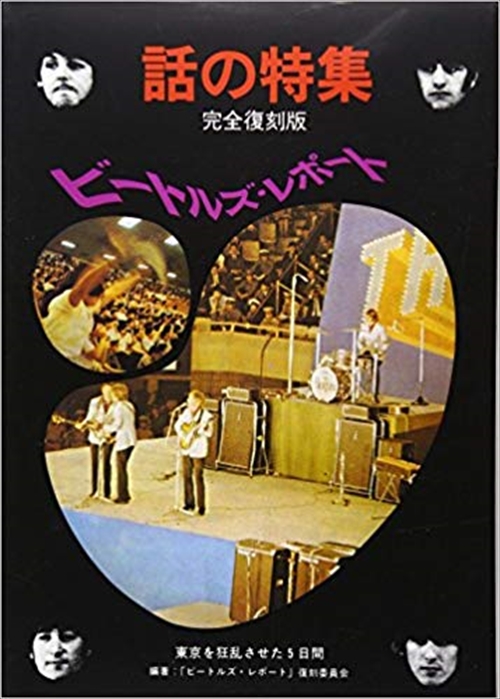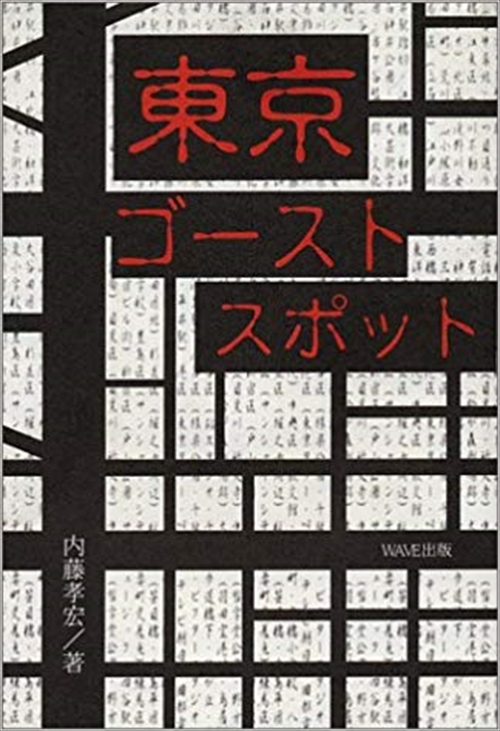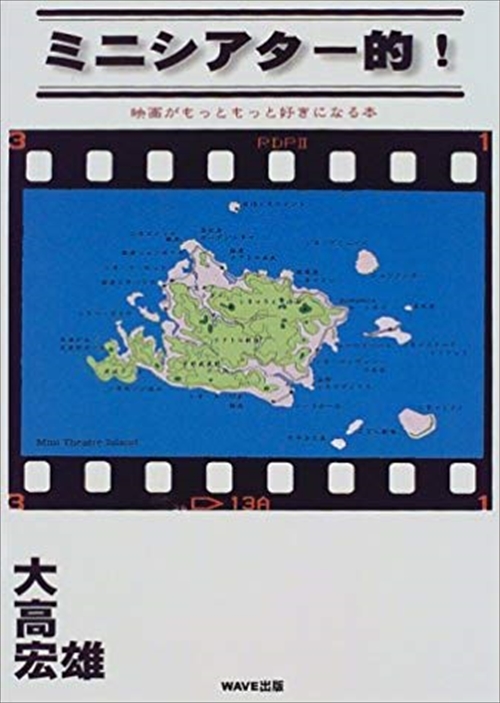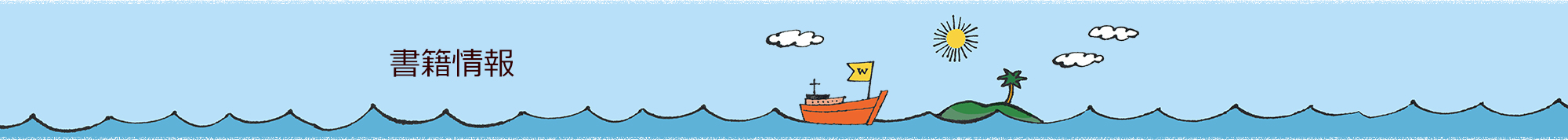
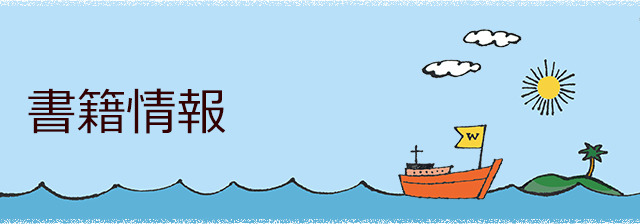
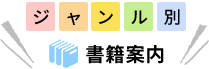

うちへ帰ろう
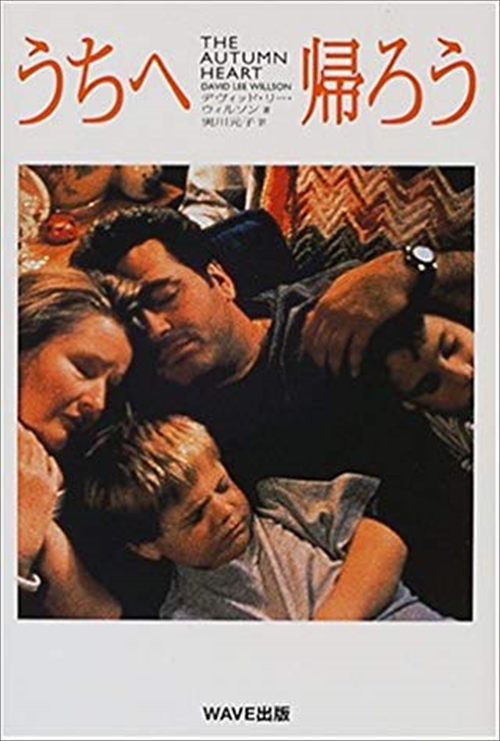
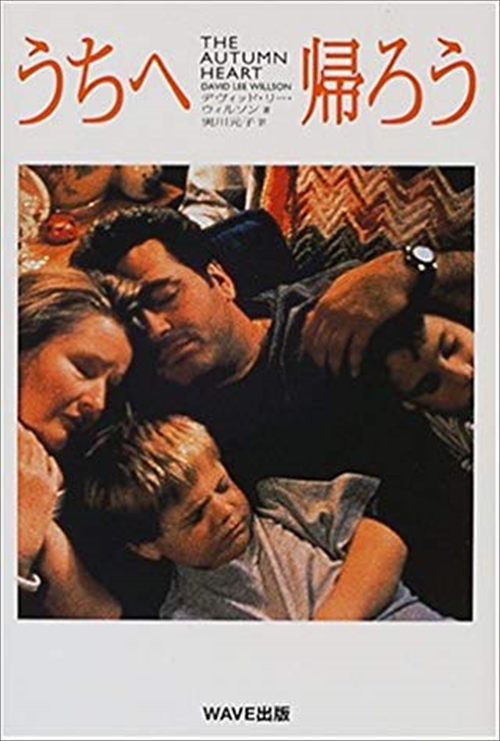
弊社在庫ございません
| ● 発行年月 | 2000年9月刊行 |
| ● 価格 | 定価 1,650円(税込) |
| ● 判型 | 四六判 |
| ● 装丁 | 上製 |
| ● ページ数 | 205ページ |
| ● ISBN | 978-4-87290-084-2 |
あとがき――「家族」はどこに帰るのだろう?
映画「うちへ帰ろう」の原題は“The Autumn Heart”である。脚本を書き、映画では末弟のダニエル役を演じたデヴィッド・リー・ウィルらソンは1999年サンダンス映画祭で、このタイトルについてこう述べた。
「母なる自然、父なる季節には四人の子どもたちがいます。冬、春、夏、そして最後の季節が秋――秋は過去に失ったものを悼む季節だとされています。私たちの社会では、後ろを振り返ったり、後悔するのはよくないこととされています。でも私はそうは思いません。過去を振り返ることによって、私たちは過ちに学ぶことができます。運がよければ出発地点に戻ってやり直すこともできるかもしれません」
映画を見た人はみな涙を流す。悲しいわけではない。押し寄せるような感動からでもない。ただ自然に涙が出てくるのだ。気持ちのいい涙である。英雄も、スターも、悪役も、聖人も賢人出てこない。それなのに、たいせつなことを教えられた気分になる映画である。過去を振り返り、もし過ちに気づいたなら、やり直す勇気を教えてくれるからだろうか。
映画は「家族の再生」を描いている。一九六○年代に結婚し七○年代に別れた父親と母親。八○年代に結婚した次女。九○年代はじめに結婚し離婚した長女。まだ理想の結婚を求めて模索している三女。そして九○年代が終わろうとするときに結婚する末の弟。この映画の背景にあるのは、アメリカの結婚と家族の四十年間にわたる激動の軌跡といってもよい。映画の冒頭でダニエルがいう。
「かつてアメリカの夫婦の半分から三分の二は離婚した」
考えてみると恐ろしい数字である。「健やかなときも病めるときも、順境にいるときも逆境のときも、互いにいたわり、互いにいつくしむ」と誓い合ったはずのカップルの二組に一組が別れるのだ。愛しているから結婚する。愛がなくなれば離婚する。そのシンプルな姿勢をつらぬいていくと、この数字につながるのかもしれない。アメリカ人にとって結婚とは何なのだろう? はたから見ていると、簡単に結婚して、簡単に離婚するように見える。それほど軽いものなのだろうか?
そうとはいえない。アメリカ人にとって、結婚が人生の一大事であることは少しも変わっていない。結婚を神聖視するからこそ、実際にはこわれてしまってまで続けることが許せないのだ。結婚が持つ重さは、四十年前からそう大きくは変わっていない。
ならば、何が変わったのだろうか? 家族観と家族の形である。結婚するのはもちろん、同棲するのも、家族がほしいからだ。結婚しなくても子どもだけはほしいという人も、家族がほしい。時代は変わっても一○○パーセントに近い人が、誰かとともに人生をおくりたいと望んでいる。ところが現在では子どもがほしければ、女性ならば人工授精で子どもを産むことも可能だ。養子を迎えることもできるし、現にその数は増えている。同性愛カップルだって徐々に社会に認められつつある。「これが家族だ!」という確固たる家族観は失われ、アメリカ社会でこの四十年間に家族は大きく様変わりした。
かつてのように、夫婦に子どもが二人、という型にはまった家族の数が急激に減ったのが七○年代以降。女性の自立志向の高まり、社会進出、キャリア追求、そして経済力向上によって、離婚家庭が急増し、家族はある意味で崩壊した。「崩壊」という言葉はもしかしたら正しくないかもしれない。たしかに愛し合っているダディとマミーがいて、週末にはダディとキャッチボールをしたり、マミーとクッキーを焼く「理想的家族像」は崩壊したかもしれない。だが、それにかわる別の家族像や形が八○年代後半から生まれつつある。父親、母親どちらか一方だけの親しかいない家庭、離婚した者同士がお互い連れ子をした再婚家庭、養子を何人も迎えた家庭、非婚カップルなど、さまざまな家族の形が生まれ、どんな形であれ「家族」と社会は認知するようになってきている。
「アメリカの家族」(岩波新書)で著者の 岡田光世氏はこう書いている。
「それにしても、アメリカは何という国なのだろう。九六%の人が結婚を望み、九○%が結婚する。そして、その半数が離婚する。それでも、『結婚はもうたくさん』というわけではなく、『相手を替えればうまくいくだろう』と、離婚経験者の七五%が再婚し、そのうち一○組に六組は離婚する。四人に一人の子どもはひとり親家庭で暮らし、半数の子どもは一八歳までのある時期をひとり親と住む。
なぜ、アメリカの家族を取り上げるのか。それは、人間の”欲望“を極限まで追い求めた姿がそこにあるからだ。アメリカ人はほしいものがあれば、勝ち取ってきた。プライバシーを尊重するこの国では、とくに家族について政府があれこれ口出しするのを、人々はよしとしない。自由をほしいままにし、権力を主張し、アメリカ人はどこに行き着いたのか。何を求めてここまで来たのか」
結婚を経済的・社会的結びつきとだけ考えなくなったときから、男も女も自分にとって一番居心地のいい居場所を模索しはじめた。アメリカは模索することを「よし」としている国である。たとえその過程で傷ついたり、傷つけられたりすることがあっても、それをプラスにして前に進むことを重視する。無理をして自分を抑えつけてまで「家族」をやっているよりは、飛び出していってもっといい場所を探すほうが勇気のある人間とみなされて賞賛される。岡田氏のいうように、個人の「欲望」を追い求めていく正直さのほうが、「忍従」よりもはるかに価値があると考えられている。
だが、そうやって個人の自由を優先する空気を疑問視する人たちが、八○年代後半から増えてきたのもたしかである。離婚によってもっとも大きく傷つくのは、夫婦ではなく子どもだ。子どもたちは、親の正直さに振り回される。夫婦喧嘩の絶えない家庭よりは、まだ片親のほうがいいだろう、というのは親側の言い分であって、子どもには伝わらないことが多い。親の離婚によって、子どもは精神的・社会的支柱を失う。離婚後、ほとんどが母親に引き取られる子どもたちは、経済的な基盤を失うことも多い。子どもにとっては、家庭は全宇宙である。親は自分を絶対的に支えている存在だ。それを半分失うことは、存在が半分なくなるほどの恐怖を味わうにちがいない。
父親なり母親が自分たちを置いて出て行ったとき、残された子どもたちは「自分にどこか悪いところがあったから、パパとママは別れたのだろうか」と悩むという。映画の中でもすでに三十五歳になっていた長女のデボラが、父親に涙ながらに訴えた。
「パパとママが別れたのは、私が悪かったの?」。
たぶんデボラの中で、両親の離婚は二十年たってもまだ決着がついていなかったのだろう。母親からは「父さんが勝手に出て行ったのよ。あんたたちと私を捨てて」と聞かされて、それを無理矢理自分に信じこませていた。だから父親が突然あらわれたときに、さんざんののしって悪態をついた。父親を一方的に悪者にしてしまうことで、彼女は両親の離婚のときに感じた恐怖に蓋をしていたのである。それなのに、母親の依頼によって裁判所が発行した「面会禁止令」を見たときに、ついにその恐怖と正面から向き合わなくてはならなくなった。「両親の離婚の原因は、自分だったのではないか」という恐怖である。
映画では父親と和解することで、デボラは自責の念からいくぶんかは救われている。だが、自分の離婚によって子どもに与えた傷をいやしていくのは、これからである。誰もがハッピーな離婚などありえない。誰もが多かれ少なかれ傷つき、苦しむのが離婚である。
だからといって、映画と同様このノベライズでも、離婚は何があってもNO! お父さんがいて、お母さんがいて、かわいい子どもたちのいる家庭こそが最高なんだ、という超保守的家族観を押しつけたいのではない。血のつながった家族って、やっぱりあったかい、最後に頼れるのは家族よね、という封建的な家族観を訴えようというのでもない。
家族は濃密な人間関係だから、傷つけあうこともあれば、ときには憎しみだって生まれる。近い関係だからこそ、誤解も生じるし、嫉妬や裏切りだってあるだろう。それでもお互い理解し、許して、愛し合っていく可能性を秘めているのも家族なのだ。夫婦はもちろん、親子といえども、たえず歩み寄って関係を保っていく努力をしていないと、腐ってしまうのも早い。そしてたとえ腐ってしまって、もしも他人だったらとても修復できそうにないほど関係がこわれたようでいても、家族ならばあらたな形で再生していくこともできる。家族が持つそんな力を描いている映画であり、ノベライズなのだ。
アメリカの家族と同様、日本の家族もいま激しい変化の波に洗われている。アメリカ人のように、愛がさめたらさっさと離婚するという潔さは日本人にはないから、離婚率は低い。だが「家庭内離婚」は確実に増加しているのではないか。家族の形もアメリカとはちがった意味で、多様化している。晩婚化の進行とともに、結婚せずに親と同居しつづけるパラサイト・シングルの増加はその顕著な例だろう。今後日本人は、家族の意味をどこに見出すのか? 家族がこわれてしまったとき、日本人ならばどうやってそれを再生させるのか? もし日本でこの映画が撮られたとしたら、結末は「父帰る」になるのだろうか?「うちへ帰ろう」というタイトルから想像されるとおりのほのぼのとしたストーリーではあるが、内容はつきつめていくと、現在のシリアスな家族の状況を示しているともいえる。映画はダニエルの語りでストーリーが進行するが、私はこのノベライズではあえて次女のドナに語らせた。一家の中で唯一結婚を継続させて、ダディとマミーと四人のかわいい子どもたちという五○年代型の家庭を築いている彼女に、両親、姉、妹、弟それぞれの結婚観を語らせたかった。何度もこわれそうになりながら、それでも必死にドナが守ろうとしている「家族」に、私はささやかな希望を見出したい。他人にうらやましがられるような理想の家族ではないかもしれないが、ドナが努力して築いていこうとしている「家族」に、これからの「家族」の一つの方向を示してもらいたい。彼女に語り部の役をふったのは、そんな思いからである。
二〇〇〇年八月 実川元子